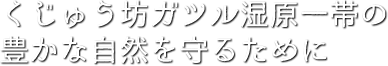2025年11月12日
2025年度秋 平治岳の『ミヤマキリシマ』植生保護活動を実施しました !!
九州電力の社有地でもある平治岳(ひいじだけ)で、「ミヤマキリシマ」植生保護活動を実施ました。
当活動は、2011年から始まり、毎年春と秋に活動を継続しており今年で15年目を迎えます。
11月1日(土)に実施した今回の活動では、環境省や地域の団体等で構成する「平治岳の自然を考える会」メンバーや九電グループの従業員と
「ミヤマキリシマ」は九州の高山のみに自生する、世界でも希少な植物です。
毎年、5月下旬~6月上旬に花期のピークを迎えますが、一斉に花を咲かせた様は、ピンク色の絨毯のようでとても美しく、迫力があります。
この希少で美しい花を守るため、九電みらい財団では、地域の皆さまとともに生育の支障となる木の伐採や登山道整備を行う植生保護活動に取
り組んでいます。
この地道な活動の継続により、2023年、平治岳周辺が環境省より「自然共生サイト」に認定されました。
※「自然共生サイト」とは、民間の取組み等によって、生物多様性の保全が図れている区域を、国(環境大臣)が認定する区域のことです。
当活動は、2011年から始まり、毎年春と秋に活動を継続しており今年で15年目を迎えます。
11月1日(土)に実施した今回の活動では、環境省や地域の団体等で構成する「平治岳の自然を考える会」メンバーや九電グループの従業員と
その家族など、86名の皆さまにご参加いただき、ミヤマキリシマの生育の支障となっている樹木の伐採や登山道の整備を行いました。
「ミヤマキリシマ」は九州の高山のみに自生する、世界でも希少な植物です。
毎年、5月下旬~6月上旬に花期のピークを迎えますが、一斉に花を咲かせた様は、ピンク色の絨毯のようでとても美しく、迫力があります。
この希少で美しい花を守るため、九電みらい財団では、地域の皆さまとともに生育の支障となる木の伐採や登山道整備を行う植生保護活動に取
り組んでいます。
この地道な活動の継続により、2023年、平治岳周辺が環境省より「自然共生サイト」に認定されました。
※「自然共生サイト」とは、民間の取組み等によって、生物多様性の保全が図れている区域を、国(環境大臣)が認定する区域のことです。
参加者の皆さまは、大船林道終点にて、作業で使用するヘルメットや太枝切バサミ、また、ハンマーやシャベル等の資機材をリュックや背負子に入れて、
辺り一面ススキに覆われている坊ガツル湿原の中を歩き、木々が色づき始め紅葉が見られる平治岳登山道を登り、適宜休憩を取りながら約2時間かけて大
戸越に向かいました。
辺り一面ススキに覆われている坊ガツル湿原の中を歩き、木々が色づき始め紅葉が見られる平治岳登山道を登り、適宜休憩を取りながら約2時間かけて大
戸越に向かいました。
支障木伐採班はミヤマキリシマの植生を驚かすノリウツギの伐採やススキを刈り取る作業を行いました。
登山道整備班は、従来工法班1班と新工法班2班構成で実施
春から秋にかけて多くの登山者が訪れる平治岳では、登山道の脇に咲くミヤマキリシマが踏み荒らされたり、雨によって登山道が崩れたりすることがあり
ます。こうした状況を守るため、既存の損傷している水切り板の補修をしたり、新たに水切り板を設置しています。
整備に必要な板や杭、ハンマー、シャベル、そして石などの資機材を担いで高所まで運ぶ作業は、非常に体力を要するものです。それでも、自然を守り、
登山者が安全に歩ける道を維持するために地道な活動を行います。
ミヤマキリシマは、くじゅう連山の春を彩る象徴的な花として知られています。しかし近年では、ノリウツギなどの樹木が繁茂することで生育環境が圧迫され、開花数の減少が懸念されていました。
こうした状況の中、地域の皆さまと力を合わせて、保護活動を地道に続けてきた結果、今年は平治岳一帯で見事な満開を迎えることができました。
この活動は、ミヤマキリシマの美しい景観を次世代へとつなぐ大切な取り組みでもあります。ご参加いただいた皆さまのご協力に、心より感謝申上げます。
来春の開花シーズンには、ぜひ平治岳へ足をお運びください。